
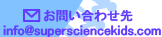
|
「子供たちが最初に出会うプログラミング環境としてスクイークはちょうどいい」 デジタルハリウッド大学学長 杉山知之さん |
||
「デジタルに対する広い想像力を身につけてほしい」今や小学校でも情報教育は当たり前になってきて、読み書きなどのデジタルリテラシーは、ある程度、いろいろな道具を使いながら学べる状態になってきました。ところが、学んでいる仕組みである、コンピュータやシステムなどが、自分で作れるものだということまでは教えられていません。このように、デジタルに対する広い世界観や創造力を持てないのは、小さいうちにプログラミングの概念を知っているかどうかが影響しています。 その点、スクイークは小学生ぐらいの子供が最初に出会うプログラミング環境としてちょうどいいと思います。視覚的で、ルールで動くし、そのルールも自分で決められる。なおかつ思ったとおりに動かないことがたくさん出てきます。たとえば、今のゲームは思い通りに動くのが当たり前なので、コンピュータは完璧だと思っている子供も少なくない。けれど現実にはそうではないことを思い知らされます。また、コンピュータが間違えるのではなく、人の誤りがそのままでるのだとわかることが重要なのです。 「小さい頃に必要なのはバランスのとれた教育」小さい頃の教育はとても大切ですが、どれだけコンピュータの勉強をやらせるかは注意深く考えたほうがいいでしょう。コンピュータの技術はどんどん良くなっているので、バーチャルな世界にもリアリティさは出せるけれど、走り回って、ころんで、けがして、といったことを十分に経験した上でサイバーワールドがあるというのを知らないと、バランスがとれなくなってしまいます。私は10歳ぐらいまでに体で味わえることは、十分に体験することが大切だと思っています。 これだけ科学技術が発達している日本に住んでいても、非科学的なことを頭から信用する子供たちがたくさん増えています。こうしたことが、算数とか理科ばなれだと騒がれているわけですが、科学的、論理的にものを考えようという教育ができていないことに問題があるのです。 たとえば、コンピュータやソフトをとんでもない使い方をするとすごいことがおきることもあるけれど、そうした偶然を創造性というのはまちがい。サイエンスというのは、基本的に人間が理解して使える知恵であり、それを検証するためにスクイークのような道具を使うということをきちんと教えてあげたい。体験と科学的な検証の両方をバランスよく学ばなければならないというのは、教育全てに言えることです。 スクイークを開発したアラン・ケイ博士は、30年も前からそれがわかっていたわけですが、今こそスクイークという環境を拡げるのは、とても意味があると思います。 「参加する人達が一緒に成長できる場になってほしい」うちの大学院生がワークショップを手伝っていますが、スクイークを教えるのはすごく大変で、ほんとうにちゃんとわかってないと、小学生にわかるように教えられないし、ごまかせない。だからこそ教えることで自分が一緒に成長できると思っています。 HPスーパーサイエンスキッズの活動が、参加する子供たちはもちろん、その親や周囲をとりまく人達にとっても、すばらしい経験になることを祈っています。 |
||
プロフィール / 杉山知之さん
デジハリ学校長ならびに同大学学長、同大学大学院学長を務める。工学博士。
87年から3年間米国のMITメディア・ラボ客員研究員として活動し、国際メディア研究財団・主任研究員などを経て、94年10月に専門学校・デジタルハリウッド設立。
2004年に「デジタルハリウッド大学院」、05年4月に「デジタルハリウッド大学」を開学。
他にもデジタルラジオ推進協会・番組審議会委員や、CG-ARTS協会、デジタルコンテンツ協会などの委員を歴任し、デジタルクリエイター育成のために幅広く活動している。
関連リンク |
||